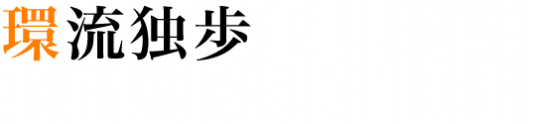爬虫類に学ぶ建築環境学 その3 2011.08.23
普段の生活の中で、我々が他の動物の存在に関心を寄せることは、そんなに頻繁にあることではないだろう。もしそうだとしても重要な意味を持つことは極めて少ない気がする。でも、爬虫類や両生類という哺乳類ではない生物に接し、彼らの生態を観察してみると、人間にとっても、温熱環境の大切さは決してないがしろにできないと思うのである。
そう考えると、ヒトのためにつくられる人工的な温熱環境というのは、ある程度の幅があっても良いのではないかとさえ思えてくる。実際、冷房や暖房の設定温度を頻繁に変えることも多いし、着衣量で暑さや寒さを調整することも可能である。犬や猫のように、飼い主に勝手に服を着させられる事例を除けば、動物たちはすべて裸体だ。
人間は、着衣量さえ変えれば、氷点下でも炎天下でも、ある程度の時間なら耐えられるようにできている。人間の体温は37℃くらいだから、それに近い温度であれば、裸のまま長時間を過ごすことができるかもしれないが、生身の状態で、15℃とかの肌寒いに状況下に置かれると、爬虫類と同じくらい意外と弱い生物なのかもしれない。
人間は着るものの量を変えることで温度調整が可能であり、また冷暖房が完備された室内にいれば、温熱環境を人工的に変化させることができる。でも爬虫類には、それはできない。生きて行くために適した環境を見つけて、そこへ移動するか、あるいはそれができずに死んでしまうかのどちらかである。
環境ということが叫ばれて久しい。その対象は地球であったり、都市だったり、あるいは極端な例を挙げると職場環境といったようにも使われるから、その範囲や概念は捉え方によって大きく異なる。そして誰もが感じるように、巨大な地球の環境を変えることは簡単にはできないけれども、身の回りの温熱環境を意識することはそれほど難しくはない。
周囲の温熱環境に気を止めたところで、諸問題が解決することにはつながらないけれども、人間は少なくとも着るものさえあれば、爬虫類よりも環境に適応できる能力を持っているのだから、それを活かすような温熱環境の制御方法こそが、環境とは何かを語る上で重要になって来る気がするのである。
例えば、ネクタイを締めて集中して仕事をする空間や、つねに締切に追われているような緊張感の高い場所で求められる設定温度と、気軽な服装で、雑談も可能な執務空間では、求められる温熱環境が異なるはずだ。ましてや、気分転換が必要になる場所は、寒かったり、暑かったりしても良いのではないだろうか。
人間の活動の種類に合わせて、空間の温熱環境にムラを生じさせるというのはどうだろうか。事務所空間において、温度も湿度も照度も、これまではつねに均一が求められて来たけれども、先述のように、設定基準に幅を持たせても良いように思う。大袈裟かもしれないが、目の前にいる爬虫類が、そう問いかけているようにさえ感じられる。
動物園にいる爬虫類は、人間と同じように冷暖房が必要である。でも、適応できるそのきめ細やかさの範囲には明らかに違いがある。猛暑が一段落し、少し涼しくなったとはいえ、まだ蒸し暑さの残る東京を歩くと、人間が求める快適性というのは、いつの間にか爬虫類が生きて行く環境と同じくらいの精度が求められているというのは言い過ぎだろうか。
人間なんだから、もっとおおらかでも良い気がする。そんな気持を受け入れてくれる空間もあれば、炎天下に置かれた車のように、冷房がないと中に入れないような空間もある。それらが混在すると、いつの間にか人間は我が侭になる気がする。我が侭になることは、おそらく地下資源を消費することに結びつく。
そんなことを考えても何の解決にもならないのだが、フランクフルト動物園からやって来た微動だにしないサイイグアナの、つぶらな遠い視線をなぜか思い浮かべてしまう。人間は温熱環境にもっと貪欲でありながら、逆に寛大でなければならない気がするという矛盾したことを最後に問題提起したまま、今回は終わりにしたいと思う。
加筆訂正:2011年8月26日(金)