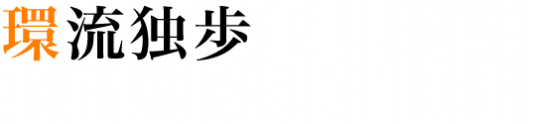設備のない建築 その3 2012.03.23
彼の気持は良くわかる。その一方で、その意匠設計者の台詞は、まったく理解できないかと言うとそうでもない。というのは、実際、多くの建築家や意匠設計者が思っている一般的なことだと考えられなくもないからだ。むしろ、設備設計者も、それなりの気概を持って仕事に取り組んではいるものの、それが意匠的な提案と整合が取れた最良の提案かどうか疑問を感じながら、設計を進めなければならないことが多々あるからだ。言い訳になってしまうが、そんな面は拭えない。
ところで、私は同期とは違うことを言われたことがある。「何で設備設計『なんて』やってるの?」。私が設備設計者として働き始めて3年目くらいのことだったろうか。誰に言われたかは伏せておくが、意匠設計に携わっている方が私にふと漏らした台詞だった。その人は私に正直な気持ちを伝えたのだろう。そのときの私は自信がなかった。だから、取り立てて腹が立つこともなかったし、何も反論しなかった。ただ、こういう人とは一緒に仕事をしたくないと思った。
建築意匠設計者に比べたら、設備設計者は地味かもしれない。いや、意匠設計が派手だとも決して思わないが、設備設計は建築を陰で支える面が大きいから、より地味な仕事に見られる面は否めない。しかし、設備設計者も、それなりの高い意識をもって仕事に望んでいるから、それを全否定するような発言は聞き捨てならない。設備設計というのは、建築の設計の中において、とても大切な役割を担っている。これは間違いない。
でも中には、日々の作業が決まりきった内容になってしまい、創造性や発展性を示さず、旧態依然のまま業務をこなしている人もいるのかもしれない。ただ、設備設計者のことを揶揄するのであれば、そういう人が設計を行なえば良いとさえ思う。いや、変な言い方になってしまうが、もしかして、それが意外とできてしまったりする可能性だってないとはいえない。だとすれば、設備設計者の存在意義が大きく揺らいでしまうことになる。
どんな建築にも設備が必要ないのであれば、設備設計者は不要になる。でもこの先、給排水設備や、冷暖房設備、換気設備、電気設備がまったくない建築というものが現れるかというと、そんなことはまずあり得ないだろう。だから、それでも設備のない建築こそ、これから求められるものだと言い切れるかと言うと、気持がかなり揺らいでしまうのだが、表現を変えれば、「設備というものに極力頼らない建築」と言い換えた方が良いのかもしれない。
これからは、設備が小さくなるような建築的工夫を行い、そして設備による地下資源の消費をできるだけ抑えた低燃費な建物を目指して行きたいと思う。それはとても難しいけれど、取り組み甲斐のあることではないだろうか。