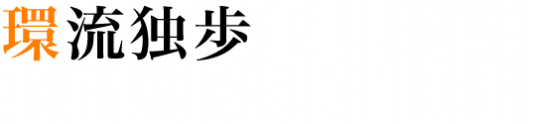リハビリ杖のお父さん 2010.03.17
3、4年くらい前のことだったろうか。ケルンでいつも行っているスーパーに買い物に出かけたときのことである。支払いを済ませたあと、買った物をリュックサックに詰めて、お店を出ようとした私に、背の高い初老の男性が声をかけてきた。「リュックサックを背負うのを手伝ってくれませんか」。両手にリハビリ用の杖を持ったその男性は、私と同じように荷物をリュックに入れて、これから背負って帰ろうとするところだった。
「ええ、構いませんよ」。私にとっては、お父さんと呼んでも構わないであろうその男性のリュックは、買った物で完全に膨れ上がっていた。それを一人で背負うには、リュックを一旦机の上かどこかに置いて、自分が屈んだ状態で両腕を通さないと難しいように見えた。「近くなら運んであげますよ」と私が言うと、お父さんは、「ありがとう。でもバスで来ているからね」と答えた。「じゃあ、バス停まで行きましょうか」と訊くと、「いや、自分で歩いて行くから大丈夫だ」という返事が返ってきた。
お父さんのリュックは予想以上に重かった。しかも背が高く腕も長いので、しっかりと背負うには時間がかかった。私はリュックを少しでも深く背負えるようにと、できるだけ上に持ち上げて、そして少しずれ上がったお父さんの上着の裾を引っ張り直してあげた。これで大丈夫だろう。お父さんは「ありがとう」と言うと、リハビリ杖を突きながら、ゆっくりとした足取りで出口に向かい始めた。私はお父さんの邪魔にならないように後ろについてスーパーを出た。「それじゃ、また」。そう言った私に、お父さんは何も答えなかった。
帰りの方向が違う私は、お父さんをバス停まで見送ろうかと思い直して、少し歩いてから後ろを振り返った。お父さんはリハビリの杖に体重をかけつつ、一歩一歩、ゆっくり前に進んでいた。時折、顔を上げて、真正面をしっかりと見つめて歩くお父さんの足取りは、しっかりと見える一方で、その後ろ姿はどことなく弱々しくも感じられた。私はお父さんのことが気になって、その姿が角の居酒屋の陰に隠れてしまうまで、教会の脇に一人立ちすくんだまま見送った。それだけのことなのに、なぜか目頭が熱くなった。
お父さんがどのような生活しているのか、私は知らない。でも私が同じような年齢になったとき、お父さんのようになれるだろうか。あんな風にリハビリ用の杖を突きながら、自分一人の力で買い物に出かける体力や気力があるだろうか。リュックを背負うのを手伝って欲しいって言えるだろうか。身体的な衰えを受け止めつつ、しっかりと前を見つめながら歩くことができるだろうか。お父さんの姿を想い出しながら、いまは想像できない将来の自分を考えた。
そして、いまの私はお父さんに何をしてあげられるだろう。そう思っても、何も思い浮かばない。浮かばないけれど、お父さんのような社会的に弱い人たちが安心して住めるような社会が、一番必要なことなのかもしれないと思った。もしそれを私がすべてつくりあげることができるのなら、そんなに素晴らしいことはないけれど、それを実現することなど到底できない。でもきっと、職業にかかわらず、何かやろうと思えばできるのだろうし、むしろ何かをしなくてはいけないのだと思う。
言い訳になってしまうのだが、いますぐにはできないにしても、いつか何らかの方法で、そんなことにかかわるべきなのではないかと、お父さんを見て感じたのである。
加筆訂正:2010年3月27日(土)/3月30日(火)/11月22日(月)