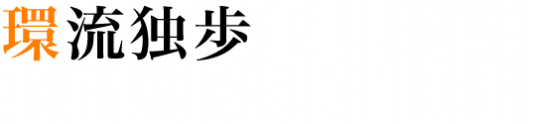仕立て屋さんのお父さん 2011.01.26
今日、洗濯に出かけたら、仕立て屋さんのお父さんにまた出会った。先月末で、お店を閉めてしまうと言っていたので、もう会うこともないと思っていたら、お店の引渡は1月末なので、まだ片付けている最中だという。ほとんど何もない状態になった店内には、服のかかっていない衣紋掛けが何本も寂しくぶら下がっている。陳列棚には古い紙箱に入ったたくさんのボタンが全部で2ユーロで売られていて、その隣りには1本5ユーロの値札がついた時代を感じされるネクタイも10本ほど並べられている。
私は先月、お父さんが使っていたアイロンを5ユーロで買ってしまった。この一か月の間にお父さんは、一体どんなものを安価に売って処分したのだろうか。それらを買いたいと言う人は実際には、どれくらいいただろう。まさに最後の在庫処分である。そういえばもうかなり前のことになるが、ケルン市内に、ありとあらゆる鉄製品を扱っていたお店を何年にも亘って撮り続けて来た写真家の写真集の翻訳をさせてもらったことがある。そのお店は閉店してしまったが、陳列棚には、いまも当時のまま鉄製品が並べられている。それを想い出した。
陳列棚に掲げられたマイスターの称号を示す証明書の日付は1953年10月23日である。お父さんの生年月日は1930年9月30日だから、22歳のときに最終試験に合格したのだ。それからほぼ60年という月日が流れようとしている。先日会ったときに、「私はもう80だから」と言っていたが、改めてこの証明書を窓越しに見ると、お父さんは60年という年月を経て正真正銘のマイスターになり、いまそれを卒業しようとしているのだろう。
世の中には数えきれないほどの職業があり、スポーツ選手が引退するのと同じように、誰もが自らの職業を離れる日がやって来る。それをどのように迎えるのか、いまの私には想像もつかないが、いつかそうせざるを得ない状況になることは間違いない。仕立て屋さんのお父さんが見せる穏やかな表情に触れると、そんなことを考えてしまう。それは決して後ろ向きな思考ではない。その先を見越した、ただの通過点の一つに過ぎない。
お父さんに袖の長さを直してもらった二着の上着を私はいまも着続けている。袖を通すたびに、お父さんを想い出すということなどないが、袖先の仕立て具合はいつ見ても完璧だ。マイスターだからあたり前に違いないけれど、60年に亘ってお父さんが手直しをしてきた数限りない仕事の中の一つかと思うと、何だか思い入れが少し強くなる。そういう何気ないものの中に隠れている職人さんの手仕事に私は憧れてしまったりする。
遥かに年下の私から、お父さんに「お疲れさま」と言うのは少々失礼だから、ともかく有難うのことばを送りたいと思う。どうかいつまでもお元気で。