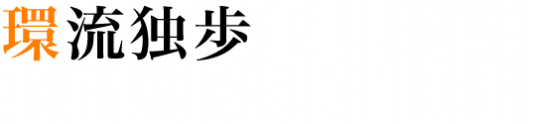楽しい日本語 その2 2011.10.10
日本語は習得するのに難しい言語だと言われている。漢字に加えて、ひらがな、カタカナがあるからだろう。しかし、話すだけなら、それほど難しくはないと聞いたこともある。それは文章を構成するときに動詞が最後に来て、しかも最後は語尾が大きく変化して終わるからかもしれない。
例えば「食べる」は「食べ」が動詞の語幹となって、そのあとが大きく変化する。場合によっては、「食べる」が語幹となることもあるが、以下に少し例を挙げればわかるように、言語は他に存在するのだろうか。しかも語尾変化によっては、一人称から三人称まですべて含まれてしまう表現さえある。
言語学者ではないから、間違っているところもあるが、面白いと感じるのは以下のような変化だろうか。
・食べ|ます 標準形
・食べ|ている 進行形
・食べ|た 過去形
・食べ|てしまった 過去完了?
・食べて|しまっていた 完了過去
・食べ|なければならない 強制形
・食べ|なさい 命令形
・食べる|な 禁止形
・食べ|ますよ 自らの行為の表明と相手への促し/一人称
・食べ|たら? 二人称への促し
・食べる|だろう 確証のない未来形/人称は不確定
・食べる|に違いない 確証の強い未来形/人称は不確定
・食べ|ようかな 自らへの疑問と相手からの返答待ち/一人称
・食べる|のかな 目の前にいる相手に対して第三者の様子を伺う/二人称と三人称
・食べ|ているらしいよ 目の前にいる相手に対して第三者の様子を伝聞する
・食べ|たかな 三人称への質問展開
こんなことを書いて何の意味があるのかと思われるかもしれないが、これまで日本とドイツを比較し、何がどう違うのかをずっと問いかけて来ることが多かった。気候風土、食文化、言語の違いは、まぎれもなく思考に影響を与えるばかりか、それらの相違は建築や住まい方にも必ず表れるはずだ。
どちらが正しくて、どちらが間違っているということではなく、どう違うかを浮き彫りにすることによって、その裏側に隠れているものが見えて来るのだと思う。建築は文化の一つであるから、表面的なことだけを見て判断したくはない。その背景を理解する必要がある。
ことば遊びの中から、それらが見えるかどうかはわからないけれど、何か面白い示唆が得られるのではないかと思っている。