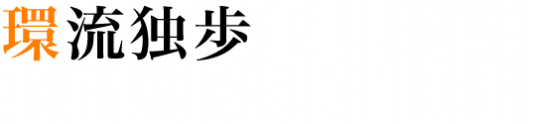暖房の方法 その5 2012.01.22
ここまで書いて来て思うことは、日本で行なわれている暖房というのは、あくまでも分散型なのだと改めて思う。先程も書いたが、ドイツのように地下室に温熱源があって、そこから各部屋に温水配管が行き渡らせ、それを放熱器に通して室内を暖めるという方式は、北海道であっても、ほとんど用いられていないのではないだろうか。札幌で建てられる集合住宅では、居間にガス栓があり、それをガスファンヒータに接続して暖房する方法も用いられているようだ。
何度も書いたように、日本の夏は暑いから、冷房による電力供給が逼迫することだけが、毎年のように取り沙汰されているが、冬の暖房に消費される化石燃料も決して少なくない。しかも各家庭で必要な一次エネルギーのうち、給湯が占める割合は3割りから4割り程度だ。室内を暖めたり、温水をつくるための熱源はどうあるべきなのか。そして、どのように暖房すべきなのだろうか。簡単そうに思えて、実はとても難しい課題ではないかと、長々と書いてきて、改めて実感している。
昔の建物には冷暖房設備というものなかった。あるとすれば、日本では囲炉裏だったり、あるいは長屋のような建物ものでは、調理場が暖房設備を兼ねていたのかもしれない。ドイツの民家でも、同じような状況だったようだ。現在では、ドイツは組積構造が大半を占めるが、中世時代には木造が中心の地域も多く、当時は調理場が一階にあったから、火災も起きていたらしい。そこで、1階は不燃である石造にすることになり、それが次第に組積造へと変化した背景がある。
また1階の調理場からの煙を、いかにして排出するかも問題になっていたため、耐熱煉瓦による煙突が発達した。そういえば、現在と過去にかかわらず、世界各国の暖房方法について考えたことがなかった気がする。一応、自らの専門分野にかかわることだから、この機会に少し調べてみることで、何か新しい示唆が得られるかもしれない。ちなみにドイツの一般住居で、温水暖房が普及し始めたのは、1900年前後のようである。
最後になって、また話が脱線してしまったが、いま、東北の南部から関東以西の一般的な住宅で用いられている冷暖房方法は、好む、好まざるにかかわらず、電力を利用したルームエアコンが大半を占めているのではないだろうか。もちろん、ガスも多く使われているだろうし、独自の冷暖房システムを提案している工務店さんや、設計事務所もあるかもしれない。化石燃料に代表される「地下資源」と、太陽や風、水という「地上資源」を、どう使っていったら良いのだろうか…。
それに対する答えは多様なのかもしれないが、一つだけ言えることは、いずれにせよ、化石燃料の消費が少なくなるような低燃費な建築を目指すことが極めて大切なのではないかと思う。日射を防ぎ、通風を考えた計画も、それにつながるはずだ。もちろん、つねにそれだけが求められるわけではないけれども、建築を取り巻く大切な視点の一つだと思うし、冷房も含めて、室内の温熱環境はどうあるべきかについて、これからもいろいろと考えて行きたいと思っている。
今日も長文にお付き合いを頂き有難うございました。
加筆訂正:2012年4月14日(土)