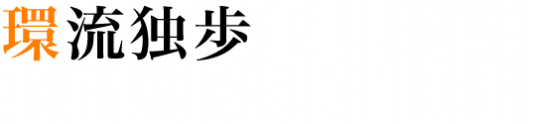昇降機の扉 2012.01.25
日本の昇降機には扉を閉めるボタンが必ずついている。あたり前だと思うかもしれないが、ヨーロッパでは、開けるボタンはあっても、閉める方はない場合が多い。その理由はわからない。エレベータは自動で動くものだから、乗ってしまった人は、希望の階に着くまで、何もしないという考えなのかもしれない。ただ最近では、「閉」のボタンもついている昇降機もかなり増えつつある。
これまでのドイツでの生活を通じて、この「閉ボタン」がない昇降機の扉の締まり方には、概ね二種類あることに気づいた。いつ閉まるのかと思うくらい動きが遅い扉と、逆に閉まるのが早過ぎるのとに大別できそうなのだ。扉の反応に時間がかかるエレベータは、人と乗り合わせると、とてもじれったい。でも、どうすることもできないから、密閉空間に漂う微妙な静けさと、隣りの人とすぐには埋められない近過ぎる距離感を感じながら上下移動することになる。
その反対で、扉の閉まりが早過ぎて、降りようとしているときに閉まりかける昇降機も問題だ。降りる人をセンサーで感知するものは反応が早いから、すぐに開くのだが、古いエレベータが多い欧州では、扉の先端から少し出ている部分を押すと止まる方式のもまだ使われているので、降りるときにドアが身体にぶつかってしまうこともある。別に痛くはないし、機械というのは組み込まれた制御以外のことはできないから、そういうものだと理解するしかない。
閉まりの遅い扉も、やけに早い扉も、どちらも実に欧州的である。だから日本で見られるように、乗って来た人が行き先階を押したあと、すぐに閉めるボタンを押したり、あるいは降りる人が閉めるボタンを押して出て行くのを見ると、日本にいることを如実に実感してしまう。それに対して、扉を自分の意思で閉めることができない昇降機に出会うと、何だか余裕のある大人が扉を開閉しているのではないかとさえ感じたりするのである。
開けるボタンはあっても、閉めるボタンがない昇降機に乗り、誰が乗って来ても、組み込まれた制御方法通りに閉まる扉の動きを見ていると、ドイツでの生活を始めた頃に感じていた先の見えない不安と、晴れることのない深く重い気持の蟠(わだかま)りというものから脱却できないまま、何もせずに塞ぎ込んでしまいそうになっていた自分をなぜか想い出す。そのときに置かれていた自分の環境は、まさに気持が毎日のように上下する昇降機であった。
その中はとても狭く、そこから踏み出したいのに、それができない自分がとてつもなく歯痒かった。答えのある階を見つけて、そこで降りれば良いのだけれど、その階を見つけることができない。降りたいのに、降りられない自分。無表情で勝手に閉まる扉。行き場のない閉塞感。実に大袈裟なのだけれど、いまにして思えば、このまま何もしないと、自分の生き方をも塞がれてしまうようにさえ感じられたのである。
まさに昇降機のように、生きていれば昇りのときもあれば下りのときもある。ドイツで静かに閉まるエレベータの扉を見かけると、そんなことに思いを巡らせてしまったりするのである。