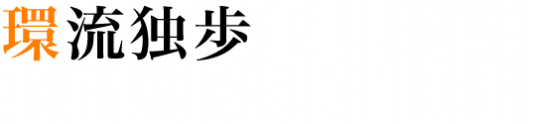雨樋と氷柱(つらら)と春の訪れ 2012.02.01
郷里の北海道から東京へ出て来たときに気がついた住まいの違いについては、すでに「塀の文化」や「洗濯機置き場」という標題で書いた。今日は「雨樋」である。簡単に言えば、北海道の家には雨樋がない。まったくないかと訊かれると、答えに自信はないが、ほとんどの家には雨樋がないと思われる。無論、落雪の問題があるからなのだが、屋根に雪を乗せたままの「無落雪住宅」が数多く建てられて来た経緯も関係しているから、北海道では雨樋というものを見かけない気がするのである。もっとも最近では、屋根の雪を落しつつ、雨だれは受けられる二つの機能を持った雨樋も使われているようだから、絶対にないというわけでもなさそうだ。
幼少期から高校生まで、北海道で過ごした私がいま想い出せることは、どの家の軒先の下にも、雨だれがつくった小さなくぼみがたくさんあったような気がする。もしかしたら、北海道だけでなく、昭和30年代とか40年代は、雨が落ちる部分には草が生えず、その周りに雑草が茂っていた光景が、日本のあちこちで見られたのかもしれない。屋根から降った雨は、どこへ流れて行っていたのだろう。北海道は土地が広いから、それほど問題にならなかったのだろうし、それはいまも同じなのだと思う。北海道には梅雨もないし、大型の台風が来ることもほとんどないから、集中豪雨に見舞われることも少ない。一年の半分弱は雪に埋もれているようなところだから、雨樋など付けても、シバレてしまって、使いものにならなかったのだと思う。
そういえば最近、屋根から大きく伸びた氷柱(つらら)を見かけることが、極めて少なくなった気がする。いまは北海道に住んでいるわけではないので、実際の状況を知るには無理があるが、帰省したときのことを想い出してみても、子供の頃に見た大きな氷柱というものが、もはやどこにも存在していないように思われるのだ。当時は、軒先からの「すがもれ」が問題となっていて、屋根からの落雪や氷柱が人の命を奪う凶器となることが大きく取り沙汰されていた。実際、そういった事故が毎年、必ず起きていたから、屋根の雪が落ちそうなところや、軒の下は絶対に歩いてはいけないと、両親や学校から厳しく注意されていた。
厳しい冬が過ぎ、外気温が少しずつ上がり始めると、屋根の雪が融けて、軒からは雨しずくが、とめどなく落ちて来る。表面が溶けて陽射しを奇麗に反射させていた氷柱も次第に小さくなり、学校の大屋根から巨大な雪の塊が音を立てて地面に落ちる音が何度も聞こえ始めると、春の訪れが少しずつ近づいていることを実感した。最近は、そんな情景に出会うことが、めっきりと少なくなってしまった気がするのだが、どうだろうか。屋根から落ちる雪解け水というのは、凍れば氷柱になって危険を生み出すけれど、その一滴(ひとしずく)には、春を迎える風情が感じられる気がするのである。
北海道といった積雪の多い地域を除けば、日本の住宅の大半に雨樋が普及してしまい、屋根から落ちる雨を眺めたり、雨音を聞くことがほとんどなくなったように思う。強く降る雨は別として、静かな雨音というのは意外と心地良かったりする。雨樋は、雨を適切に流すという重要な役割を持っているけれど、少し合理的すぎるような気もするのだ。コンクリートの護岸で固められた川よりも、自然の中を蛇行しながらゆっくり流れる川の方が魅力的に思えるのと同じように、屋根から落ちる雨音を聞きながら、雨水の行方を眺めることができれば、それも悪くないのではないかと思っている。むしろ、そんな光景を目にしなくなったことで、大切な何かを失ってしまったのかもしれない。