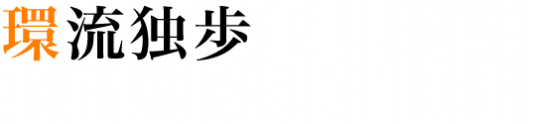設備と建築の形 その1 2012.02.04
いま設計協力を行なっている物件の図面と工事見積書を見た。あたり前のことだが、その中の設備工事の部分には、上水や下水、エアコンの冷媒管や凝縮水を流す配管の長さと、それぞれのメートル単価が書かれていて、各項目ごとに、その工事費が見積もられている。配管の他にも、屋外の地面に埋設する排水枡が7個、雨水の集水枡が8個と記入されている。これらのすべてをなくすことは無理だけれども、配管を短くし、枡の数を減らすことができるような設計変更を行なえば、その分だけ工事費は確実に安くなる。
これが何を意味するかというと、良く言われるように、水廻りはなるべくまとめて、可能であれば上下階も同じような位置に配置すべきであることを示している。そうすれば、排水は建物の一つの側だけで済む場合が多く、排水管の長さも枡の数も減らすことができる。例えば、排水が住宅の南北や東西といった離れた側に別々にあると、その分だけ排水径路は長くなから、それに比例して、工事費も高くなって行く。建築の設計は、それだけを考えて進めるわけではないが、実はとても重要な視点だと思う。
同じように、屋根から流れ落ちる雨水を考えてみる。切り妻屋根の場合、雨樋は屋根面が見える平入(ひらいり)側に必要になる。それを受けて流す雨水配管も同様に両側に設けなければならない。一方、片流れの屋根の場合だと、雨樋が必要になるのは、一つの側だけだし、雨水排水管も同じだ。つまり、切妻屋根と、片流れ屋根の雨水排水設備工事費を比較すると、極端な話、倍の差が生じることになる。私は切妻や寄棟屋根を否定しているわけではない。単に、雨樋の長さが短いほど、雨水排水設備に必要な工事費が安くなるということを指摘したいのである。
住宅にとって、屋根の形は非常に重要である。設計事務所は、どのような屋根をかけるべきか模型を作成して、いくつもの事例を検討する。勾配はこの程度で、向きはこちらの方が奇麗に見えるといったことを少しずつ詰めて行き、そして最終的な決定段階では、間違いなくそういった意匠的な面が大きく関係して来るに違いない。だから、屋根の形状に排水設備という視点が関わることは、平面的に大きな屋根が必要な建物を除いて、ほとんどないといって良いだろう。しかし、予算が非常に厳しい住宅の場合、設備的な視点も加えて屋根の形状を考えてみると、設備を優先したデザインというものが生まれて来たりする。
加筆訂正:2012年2月20日(月)/3月5日(月)