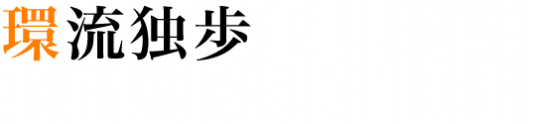明るさの再考 その1 2011.05.10
3月の震災以来、省エネルギーや節電があちこちで取り沙汰されている。あいにく日本の状況を未だ体験していないので、実はとても後ろめたい気持が心の片隅で燻(くすぶ)り続けている。特に無計画停電だと揶揄された状況の中では、東京の街はどこへ行っても暗くなったと聞いたが、実際、どの程度だったのかを知ることもできなかったし、現在の状況もまだわかり得てはいない。
ところで、震災が起きる前から「明るさ」というものについては何度もここで触れて来た(例:白熱する電球論争)。均一な照度が求められる空間もあれば、ある程度の光と陰影が必要な場合もある。そして夜になれば、電気がないと明るくできないのも事実だ。でも本当に必要なのものは「明るさ」であって「電気」ではないと思う。その空間に求められる明るさというものが何であるかを真剣に考えると、それを満たしてくれるものは電気だけとは限らない。
これも以前に触れたが、日本には提灯(ちょうちん)や行灯(あんどん)といったほのかな明るさの文化が確実にあった(例:ろうそくの輝き)。いや実際のところ、それしかなかったのだから、文化という表現を使うのは言い過ぎかとは思うが、戦後の時代により明るさを求めてきた流れと比べると、それは昔の生活の中にやむを得ず息づいていた陰の文化と言い換えられるのかもしれない。
再度、自分にも問いかけてみる。空間に陰があることは貧しいことだろうか。明るいことは真の豊かさなのだろうか。日本の多くの執務空間では、昼も夜も天井に設けられた蛍光灯からの光が常に欠かせない状況にある。打合せや何かの作業をする場所は、ある程度の照度が必要かもしれないが、いまや誰もがPCの前に座っている。もはや無駄な照度は不要ではないかとさえ思う。
そして、同じ照度を得ながら節電できる照明器具に切り替えようという動きが活発化していてる。工場や病院、商業施設建物ではそれでも良いかもしれないし、LED照明に変えることも大切だろう。しかし、これまでと同じ光環境を得るために、照明器具を節電型のものにすることがすべての解決に果たしてつながるのだろうか。そう考えるとき、必要な明るさとは何かということにこだわってみたくなる。
本来なら、昼間は太陽からの自然の光をできるだけ導き入れて、人工照明は補助的に使うべきではないかと思う。日射が直接入って来て眩しかったり暑かったりしたら、それを適度に制御し、光だけを取り込む方法も求められて良いはずだ。でも残念ながら、多くの建物がそうなってはいない。蛍光灯をつければ、外の光環境の変化に左右されない均一な照度が得られる。無論、それは夜間のためでもある。
日常生活の中で、照明器具のスイッチのずっと先に発電所があることを常に頭に描いている人は、私も含めてほとんどいないだろう。でもその電気は、確実に発電所からやって来ている。発電効率が50%近い最新の火力発電所であっても、得られる電力と同じ熱量が環境に捨てられ、その効率が30%である原子力発電所においては、得られる電力の二倍の排熱が海に捨てられている。そうしないと電気というものが得られないのである。