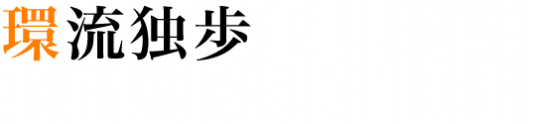本日、エネクスレインは、2007年の開設から5年目の節目を迎えました。誠に月並みな表現で恐縮ですが、これも一重に、本当に多くの方々から、ご支援を頂けたからに他なりません。心より厚く御礼申し上げます。
大家さんから許可を頂き、汗だくになりながら、事務所の壁を黄色と青色に塗り分けた、あの暑かった夏から5年という月日が流れました。その長さを、自分自身でもまだ実感できずにいます。
毎年、この日を迎えてきましたが、今回は何だかとても感慨深いものがあります。誰しも人生には転機というものが何度か訪れるものですが、私にとって、今日は大きな意味を持つ一日になりそうです。
この5年間にできたこと、そして、できなかったことを考えると、思い描いていた以上に歩みが遅く、自分でも愕然としてしまうのですが、この5年間に多くの方々から、たくさんのことを学ばせて頂いたように思います。
開所式には、暑い中、本当に多くの人に来て頂きました。それは事務所を開設できたこと以上に大きな喜びであり、また、これから始まる歩みに大きな責任も感じました。あのときのことは、いまも強く脳裏に焼き付いています。
そして、昨年も書いたように、何もしなくても、今日から次の5年に入り、10年目に向けての日々が始まります。いままでに感じることのなかった重圧のようなものを抱えつつも、これからさらに邁進して行きます。
その気持と御礼をお伝えしたく、これまでお世話になった方々に、書面での挨拶をしたいのですが、この場にての報告とさせて頂く旨、どうかお許し下さい。
暑い夏が続きます。皆さま、どうかくれぐれもご自愛下さい。
2012年7月25日(水) エネクスレイン代表 小室大輔