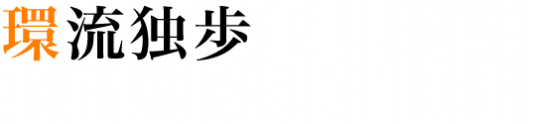人は、質問されてから真剣に考えることも意外と多いと思う。日本で普通に生活している日本人同士では、互いに質問などしないことを、違う価値観を持つ海外からの人に問われると、答えるには難いことがなぜかたくさんある。それは楽しい内容のものもあれば、重い場合もあるだろう。この国の、過去、現在、未来に対して、はたして私は明確な意見を持っているだろうか。両親は、兄弟は、親戚は、友人は、知人はどうなのだろう。
ドイツでは、韓国からの留学生にもたくさん出会った。あえて砕けた表現を使わせてもらうなら、男性も女性も、みんな気持の良い奴らばかりだった。そのうちの二人とは、いまでも連絡を取り合う仲になった。彼らとドイツビールを飲みながら、互いの国のことをたくさん話した。互いの未来のことを語るためには、過去を振り返えざるを得ない。そんなことに触れる必要もないのかもしれないが、触れないと深く知ることはできない。
ドイツ語を通じて、彼らとアジアの歴史を語り、互いの国の良いところと、負の面について議論した時間というのは、もう10数年前のことになるけれども、いまにして思えば、実に貴重な経験だったと思う。実直に話したところで喧嘩になることもない。むしろ、何にも増して楽しかった。そして、戦争を体験した世代と、いまの世代との間には、過去の歴史に対する認識も大きく異なっていることも伺えた。
ドイツに来て思ったことは、日本も韓国も台湾も中国も、その他のアジアの国は、欧州から見れば、所詮、極東の国にすぎないということなのだ。いがみあっても何も生まれない。困っていれば助け合い、楽しいことや嬉しいことを共有する。それは何もアジア人同士だからではない。もちろん場合にも寄るけれども、自分の国を遠く離れてドイツに来た者同士は、何かあったときには仲間意識が強くなる。
毎年、この日を迎えると、その日のことを必ず想い出す。そして、多くを語り合った日のことに想いを巡らせてしまう。それは過去を振り返ることではない。未来を考えることにつながるのではないかと強く思うのである。